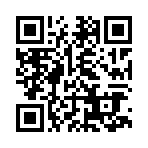2014年10月16日
夢だったロングトレイル・4
4日目 天狗山荘~ 9月19日
翌朝。いつもより遅い4時起床、すでにパッキングは済ませておいたのでゆっくりめ。
自炊は本館から出て売店兼食堂にて。外に出ると昨日までの風は収まりそよ風程度、空は満天の星空…でも寒い。
引き戸を開けて真っ暗な部屋に入ると、土間で寝ている人が・・・
前夜、ツェルトでテント泊していたが風で潰されおまけに寒すぎて、スタッフに断り避難してきたという。確かに寒かった。夕方、山荘の前に常時流れている水場には薄氷がはっていた。

翌朝。いつもより遅い4時起床、すでにパッキングは済ませておいたのでゆっくりめ。
自炊は本館から出て売店兼食堂にて。外に出ると昨日までの風は収まりそよ風程度、空は満天の星空…でも寒い。
引き戸を開けて真っ暗な部屋に入ると、土間で寝ている人が・・・
前夜、ツェルトでテント泊していたが風で潰されおまけに寒すぎて、スタッフに断り避難してきたという。確かに寒かった。夕方、山荘の前に常時流れている水場には薄氷がはっていた。

ささっと朝食を済ませ朝焼けの白馬の道を歩こう。
山小屋での一夜は布団で寝れたこともあったのか、一度も途中で起きることなく朝を迎えることができた。荷物も軽く、体調も万全、足取り軽やかだ。
鑓ガ岳を越え杓子岳をトラバース。道標には「えびのしっぽ」が付いている。

歩くときは少し寒いくらいが丁度良い。寒ければペースを上げて歩けば良い。砂礫の道をどんどん歩く。

これから先、鹿島槍ガ岳~天狗の頭までのような岩場はなく、雪倉山頂付近まで快適な稜線歩きができるであろう。
頂上宿舎を巻いて白馬山荘でしばし休憩。

そして白馬岳山頂へ。
凍てついた白馬岳山頂には数人の登山者がいて、自らが辿ってきた道程を確認しているようだ。自分も振り返りつつ、これからの行程に思いを馳せる。

三国境。遠くに赤い屋根の建物が見える。あれが朝日小屋だろうか、遥か彼方にあるように見える。

果たして辿りつくことができるだろうか…手前には雪倉避難小屋があるが、ここからだとわずかな距離で中途半端である。
三国境を過ぎると人けはまったく無くなった。ラジオのスイッチを入れる。視界をさえぎる物の無い、岩とハイマツがあるだけの道を偶然に流れてくる曲に合わせ鼻歌交じりに行く。
鉢ヶ岳をトラバースして、雪倉岳との鞍部の避難小屋に10時到着。

休憩を兼ねて小屋を見学。
風雪に耐えられるように片側には石垣が積まれ、窓は少ないがトイレもあり、なかなか立派な小屋である。掃除も行き届き清潔感がある。気軽に利用してみたい衝動に駆られるが、あくまでも避難小屋ということで緊急時のみの使用とのこと。旅先でそう言う機会には遭遇したくないが、自分を含め登山者には心強い備えだと思う。
見学後、雪倉岳の山頂を目指す。山頂に近づくと広い大地と青い空の距離が近くなって行くように感じられ、開放感が心地よい。

自分は最初から登山を志した訳ではなく、憧れていたのは海外のバックパッキングだった。だから最初に買ったザックはケルティーのフレームパック。これで槍・穂高も登ったが岩場には向かなかったため、使用する機会が減り、そのうち生地の裏のコーティングは加水分解し、使えない訳ではないが今では部屋の飾りと化している。でも原点であるこのパックは今でも大事なアイテムである。
天狗平から雪倉岳までの道はなんだか自分が夢を描いていたバックパッキングルートみたいで楽しく、自然と笑みがこぼれていたに違いない。アウトドアに憧れていた少年時代に戻った気がした。
10時40分、雪倉岳到着。

場所を示す道標は黒御影石っぽい物でできていて白馬界隈の黄色のそれとは違っていた。北に目をやると赤男山、朝日岳、朝日小屋が見える。ここから長い下りが始まる。道も砂礫から土に、植生も変わって7、8月に歩いていれば沢山の花々を楽しめることだろう。
赤男山のトラバース手前でテントが2張できるくらいの広場と枯れた沢があり、12時だったので休憩をとることにする。休んでいると朝日岳方向から登山者がやってきて二言三言交わし雪倉岳の方面に向かっていった。雪倉岳山頂はガスに覆われもう見えなくなっていた。
燕岩を通りしばらく歩くと湿地帯に入ったようで木道が現れ、やがて白馬水平道分岐に到着する。

朝日岳は明日登ることになるので迷わず水平道を選択したが、水平とは名ばかり、小さなアップダウンが多い道であった。木道が無い道で場所によってはぬかるみ、掘れていて歩きづらい・・・
どの登山道全般的に言えるが、雨が降ると地面に吸い込まれない水は低いところに流れ、登山道がその流れになってしまうことが多い。特に土の多い樹林帯では水と一緒に土が流され掘られてしまい痛んでしまう。急登な場所だと顕著で、丸太等で階段状に土留めしても焼け石に水。登山道維持と整備には莫大な労力と金額がかかるのだ。
今回ストックを使って歩いているが、その使い方も考慮する必要がある。朝日岳周辺にある湿地帯の多くに植生を守るため木道が敷設してある。その木道のほとんどはヘリコプターで運ばれたもののようだが、ストックの石突にキャップをせず突いてしまうと穴が開き、そこから早く腐ってきてしまう。莫大な費用をかけてもこれでは寿命を縮めてしまう。気をつけなくてはいけない。
そんなことを漠然と考えながら歩くが、そろそろ疲れも出てきたのか本日のコースの中で一番辛いと思った。早く着かなくても良い、小まめに休憩を入れながらあせらず歩くことに努める。
ガレ場を抜けようやく水谷のコルの木道に出て左に行くとだんだん小屋に近づいてきた。

14時40分朝日小屋到着。天狗山荘から9時間40分だった。

休憩してから小屋でテントの受付して設営。テント場は空いていてどこでも張れる状態だ。
同じテント場には自分と同じ単独行の登山者いて、その方は村営頂上宿舎から来たという。翌日の行動を聞かれ、行けるなら白鳥避難小屋まで行きたい旨を伝えた。
朝日小屋から白鳥避難小屋までコースタイムは11時間…
果たしてたどりつけるのか。手前には栂海山荘もある。もし駄目でもそこに泊まればいいだろう…

いろいろ考えながら食事を済ませ早めに休んだ。辺りはガスに包まれ星は見えない。…つづく
山小屋での一夜は布団で寝れたこともあったのか、一度も途中で起きることなく朝を迎えることができた。荷物も軽く、体調も万全、足取り軽やかだ。
鑓ガ岳を越え杓子岳をトラバース。道標には「えびのしっぽ」が付いている。

歩くときは少し寒いくらいが丁度良い。寒ければペースを上げて歩けば良い。砂礫の道をどんどん歩く。

これから先、鹿島槍ガ岳~天狗の頭までのような岩場はなく、雪倉山頂付近まで快適な稜線歩きができるであろう。
頂上宿舎を巻いて白馬山荘でしばし休憩。

そして白馬岳山頂へ。
凍てついた白馬岳山頂には数人の登山者がいて、自らが辿ってきた道程を確認しているようだ。自分も振り返りつつ、これからの行程に思いを馳せる。

三国境。遠くに赤い屋根の建物が見える。あれが朝日小屋だろうか、遥か彼方にあるように見える。

果たして辿りつくことができるだろうか…手前には雪倉避難小屋があるが、ここからだとわずかな距離で中途半端である。
三国境を過ぎると人けはまったく無くなった。ラジオのスイッチを入れる。視界をさえぎる物の無い、岩とハイマツがあるだけの道を偶然に流れてくる曲に合わせ鼻歌交じりに行く。
鉢ヶ岳をトラバースして、雪倉岳との鞍部の避難小屋に10時到着。

休憩を兼ねて小屋を見学。
風雪に耐えられるように片側には石垣が積まれ、窓は少ないがトイレもあり、なかなか立派な小屋である。掃除も行き届き清潔感がある。気軽に利用してみたい衝動に駆られるが、あくまでも避難小屋ということで緊急時のみの使用とのこと。旅先でそう言う機会には遭遇したくないが、自分を含め登山者には心強い備えだと思う。
見学後、雪倉岳の山頂を目指す。山頂に近づくと広い大地と青い空の距離が近くなって行くように感じられ、開放感が心地よい。

自分は最初から登山を志した訳ではなく、憧れていたのは海外のバックパッキングだった。だから最初に買ったザックはケルティーのフレームパック。これで槍・穂高も登ったが岩場には向かなかったため、使用する機会が減り、そのうち生地の裏のコーティングは加水分解し、使えない訳ではないが今では部屋の飾りと化している。でも原点であるこのパックは今でも大事なアイテムである。
天狗平から雪倉岳までの道はなんだか自分が夢を描いていたバックパッキングルートみたいで楽しく、自然と笑みがこぼれていたに違いない。アウトドアに憧れていた少年時代に戻った気がした。
10時40分、雪倉岳到着。

場所を示す道標は黒御影石っぽい物でできていて白馬界隈の黄色のそれとは違っていた。北に目をやると赤男山、朝日岳、朝日小屋が見える。ここから長い下りが始まる。道も砂礫から土に、植生も変わって7、8月に歩いていれば沢山の花々を楽しめることだろう。
赤男山のトラバース手前でテントが2張できるくらいの広場と枯れた沢があり、12時だったので休憩をとることにする。休んでいると朝日岳方向から登山者がやってきて二言三言交わし雪倉岳の方面に向かっていった。雪倉岳山頂はガスに覆われもう見えなくなっていた。
燕岩を通りしばらく歩くと湿地帯に入ったようで木道が現れ、やがて白馬水平道分岐に到着する。

朝日岳は明日登ることになるので迷わず水平道を選択したが、水平とは名ばかり、小さなアップダウンが多い道であった。木道が無い道で場所によってはぬかるみ、掘れていて歩きづらい・・・
どの登山道全般的に言えるが、雨が降ると地面に吸い込まれない水は低いところに流れ、登山道がその流れになってしまうことが多い。特に土の多い樹林帯では水と一緒に土が流され掘られてしまい痛んでしまう。急登な場所だと顕著で、丸太等で階段状に土留めしても焼け石に水。登山道維持と整備には莫大な労力と金額がかかるのだ。
今回ストックを使って歩いているが、その使い方も考慮する必要がある。朝日岳周辺にある湿地帯の多くに植生を守るため木道が敷設してある。その木道のほとんどはヘリコプターで運ばれたもののようだが、ストックの石突にキャップをせず突いてしまうと穴が開き、そこから早く腐ってきてしまう。莫大な費用をかけてもこれでは寿命を縮めてしまう。気をつけなくてはいけない。
そんなことを漠然と考えながら歩くが、そろそろ疲れも出てきたのか本日のコースの中で一番辛いと思った。早く着かなくても良い、小まめに休憩を入れながらあせらず歩くことに努める。
ガレ場を抜けようやく水谷のコルの木道に出て左に行くとだんだん小屋に近づいてきた。

14時40分朝日小屋到着。天狗山荘から9時間40分だった。

休憩してから小屋でテントの受付して設営。テント場は空いていてどこでも張れる状態だ。
同じテント場には自分と同じ単独行の登山者いて、その方は村営頂上宿舎から来たという。翌日の行動を聞かれ、行けるなら白鳥避難小屋まで行きたい旨を伝えた。
朝日小屋から白鳥避難小屋までコースタイムは11時間…
果たしてたどりつけるのか。手前には栂海山荘もある。もし駄目でもそこに泊まればいいだろう…

いろいろ考えながら食事を済ませ早めに休んだ。辺りはガスに包まれ星は見えない。…つづく
Posted by うまそう at 19:43│Comments(0)
│9月・北アルプス