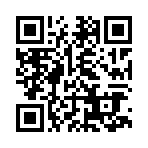2014年10月18日
夢だったロングトレイル・5
5日目 朝日小屋テント場~ 9月20日
翌朝。いつものように3時半起床、食事を済ませ撤収。
4時半に出発、朝日岳に向かう。曇り空だが明るくまずまずの天候だったが、霜が降りていた。
こういうとき木道は滑りやすいので足元に注意しながら歩く。
慣れてきたのか、歩くという行為に体が反応するように思う。日常の出来事のように「歩く」ことがパターンとしてインプットされたようだ。

翌朝。いつものように3時半起床、食事を済ませ撤収。
4時半に出発、朝日岳に向かう。曇り空だが明るくまずまずの天候だったが、霜が降りていた。
こういうとき木道は滑りやすいので足元に注意しながら歩く。
慣れてきたのか、歩くという行為に体が反応するように思う。日常の出来事のように「歩く」ことがパターンとしてインプットされたようだ。

山頂で雲の切れ間から朝日がのぞく。これから向かう先の日本海方面には雲海が広がっている。行程の最中、天候悪化しないことを願う。

朝日岳を下ると五輪尾根との分岐、吹上のコルに到着。

栂海新道を開拓した「さわがに山岳会」の名を冠した道標があった。

風雪に耐えられることを考慮してか、ステンレスの板に文字部分が彫り抜いてありいかにも丈夫そうだ。いよいよ憧れの栂海新道に入ったのだと実感した瞬間でもあった。
この辺りから湿地帯のエリアに入る。夏の時期なら花が咲き誇り美しい景色となったであろうが秋から冬に移ろうとしている今、ちょっと寂しい風景。

天気は回復傾向のようで長栂山から富山・入善だろうか、町並みが見える。まだまだ海まで遠いように感じる。

黒岩平に向かって歩く。

湿地帯は所々木道が施工されていない箇所があり、ぬかるっていた。前日の白馬水平道でもぬかるみがあったので事前に汚れ防止でスパッツを着けていたのでドロドロになるのを防げた。

やがて栂海新道と中俣新道との分岐に到着。ここを過ぎるとエスケープルートはもう無い。

体力的に問題は無かったがひとつ心配事があった。足裏の拇指球が痛くなっていたのだ。バランスが良くないのか普段から立ち位置がつま先方向にあり、親指と小指の付け根の皮が踵より厚くなっていた。インソールを変えないと、と思っていたが今回はノーマルソールのままで来てしまっていた。悔やんでも仕方がない…だましだまし歩こう。
地図を見て確認、気合を入れて先に進んだ。黒岩山山頂は分岐点からすぐのところだった。
稜線にかかっていたガスが薄くなり視程も良くなってきた。周りの立ち木の高さも低く視界も良い登山道が伸びていく。

歩いているとガサガサ音がする。何だろう?と思って足元をみると紐のような物が茂みにスルッと入って行く…蛇だ。日光浴でもしていたのだろうか、明るい犬ヶ岳に向かう道で何匹もの蛇に遭遇した。

サワガニ山到着。

稜線の北側斜面のガレている形が髑髏にみえる。こんなガレ型も面白いと思った。

休憩しながら先の道に目を懲らすと犬ヶ岳の横に赤い屋根の栂海山荘が見えた。(矢印)

下っていくと北又ノ水場分岐に到着。
情報によると黒岩山から白鳥小屋までに北又ノ水場、黄連ノ水場、白鳥小屋直下の水場と3箇所ある。いずれにしても水を補給していかないと小屋には備えは無いので何処かには寄って行かなくてはいけない。黄連と白鳥は枯れることもあるとのことで北又は問題ないらしいが、今朝出発した朝日小屋の情報では黄連も大丈夫とのことだった。自分の場合は夕、朝食、行動用に2リットルは必要で、できれば泊まる予定の場所から近いところのほうが重くならなくて歩くには楽ができる。
この時点では拇指球の痛みはさほどでもなく、この分なら栂海山荘には泊まらなくてもよさそうだ。ということで北又はパスすることにした。
崩れかかったヤセ尾根を通り犬ヶ岳に到着。

目の前に小屋が見え、更に遠く、一番奥の山の上になにやら光っている構造物が小さく見える。

あれが白鳥小屋なのか…?ものすごく遠くに感じ、なんだか気持ちが折れそうになる。
栂海山荘12時到着。朝日小屋から既に7時間半たったことになる。

休憩を兼ねて栂海山荘を見学。声をかけたが誰もいなかった。
入り口は二つあり、入ると土間、テーブルがある。テーブルのところにはこの建物の歴史写真があって歳月と共に小屋が大きくなっていく様がわかる。献金箱があり一泊2000円とのこと。土間のところには荷物置き場があってその奥に山小屋のような蚕棚のベットがあり、毛布が備えられている。


表のベンチに腰掛けながら、迷った。ここから先、白鳥小屋までのコースタイムは3時間半。休憩も入れると4時間はかかるだろう。時間が遅くなれば疲労も溜まり、さらに時間はかかるかも知れない。足の拇指球も心配だ。予備日はみているが白鳥まで行ければ翌日は楽になるだろう。仮にたどり着けなくとも途中でテントを張れば良い…などなど考えて結局、白鳥を目指すことにした。
栂海小屋からの下りは急でしかも長い。この辺りから樹林帯に変わっていく。そして登山道は土っぽくなり、所々ぬかるんでいたためスリップし易い。もし雨が降っていたら大変だったろう。
黄連山を越えて黄連ノ水場分岐到着。

白鳥の水場は枯れているかも知れないのでここで補給することにした。往復10分とのことだったが時間はもっと短かった。水の流れはほとんどなかったが、ダムのように堰き止められていた水溜りから汲んだ。
ザックに入れ背負ってみると明らかに重くなっていた。わずか2kgでも疲労した体には堪える。そんな気持ちを癒してくれたのは辺り一面のブナの林だった。
新潟の十日町に「美人林(びじんばやし)」というブナ林の名所がある。人間の手は入っているのだろうがそれは美しい林で、木が、森が、美しいと感じたのは初めてだった。黄連山周辺のブナは高さは無かったがやっぱり美しかった。
黄連、菊石、下駒ケ岳、白鳥とピークを越えるように道が作られているが「朝日から歩き始めて最後にこのピーク越えは本当に辛いよ」とは聞いてはいた。歩くと下りは拇指球が痛く大変だが登りは問題なし。ずっと登りが続けば良いと心の底から思っていた。
菊石山を下り、下駒ケ岳の基部で休憩。靴を脱いで足を休ませる。体力的には問題無いのに登る前からわかっていたのに、後悔先に立たずとはこのこと。帰ったらインソール真剣に考えよう・・・
トラロープがある急登を登り、ガレ場を歩き下駒ケ岳14時25分到着。

白鳥小屋まであとどのくらいなんだろう?ふと顔を上げたび、木々の間から白鳥小屋が見えるがまだ遠いように感じる。
白鳥の水場。水は黄連で汲んできたから必要ないのでスルーしたが、改めて水の重みが体に圧し掛かる感じがする。
空が近くなってきている。確実に高度を稼いでるのは分かるが、上がったり下りたりしているので次のピークの先にゴールがあるのか分からない。
このピークの先にもまだ道が・・・と思ったら、白鳥小屋到着。なんだか拍子抜けした本日のゴールだった。

15時30分、朝日小屋から11時間だった。
小屋に荷を降し登山靴、靴下を脱ぎ捨て、サンダルに履き換える。開放感がたまらない・・・
固まった体を解し、建物の上にある展望台に上った。

目の前に日本海が広がる。天気も良く能登半島も確認することが出来た。
小屋には自分ひとり。この時間だ、貸しきりで泊まらせてもらうことになるのだろうと、思っていたら・・・つづく

朝日岳を下ると五輪尾根との分岐、吹上のコルに到着。

栂海新道を開拓した「さわがに山岳会」の名を冠した道標があった。

風雪に耐えられることを考慮してか、ステンレスの板に文字部分が彫り抜いてありいかにも丈夫そうだ。いよいよ憧れの栂海新道に入ったのだと実感した瞬間でもあった。
この辺りから湿地帯のエリアに入る。夏の時期なら花が咲き誇り美しい景色となったであろうが秋から冬に移ろうとしている今、ちょっと寂しい風景。

天気は回復傾向のようで長栂山から富山・入善だろうか、町並みが見える。まだまだ海まで遠いように感じる。

黒岩平に向かって歩く。

湿地帯は所々木道が施工されていない箇所があり、ぬかるっていた。前日の白馬水平道でもぬかるみがあったので事前に汚れ防止でスパッツを着けていたのでドロドロになるのを防げた。

やがて栂海新道と中俣新道との分岐に到着。ここを過ぎるとエスケープルートはもう無い。

体力的に問題は無かったがひとつ心配事があった。足裏の拇指球が痛くなっていたのだ。バランスが良くないのか普段から立ち位置がつま先方向にあり、親指と小指の付け根の皮が踵より厚くなっていた。インソールを変えないと、と思っていたが今回はノーマルソールのままで来てしまっていた。悔やんでも仕方がない…だましだまし歩こう。
地図を見て確認、気合を入れて先に進んだ。黒岩山山頂は分岐点からすぐのところだった。
稜線にかかっていたガスが薄くなり視程も良くなってきた。周りの立ち木の高さも低く視界も良い登山道が伸びていく。

歩いているとガサガサ音がする。何だろう?と思って足元をみると紐のような物が茂みにスルッと入って行く…蛇だ。日光浴でもしていたのだろうか、明るい犬ヶ岳に向かう道で何匹もの蛇に遭遇した。

サワガニ山到着。

稜線の北側斜面のガレている形が髑髏にみえる。こんなガレ型も面白いと思った。

休憩しながら先の道に目を懲らすと犬ヶ岳の横に赤い屋根の栂海山荘が見えた。(矢印)

下っていくと北又ノ水場分岐に到着。
情報によると黒岩山から白鳥小屋までに北又ノ水場、黄連ノ水場、白鳥小屋直下の水場と3箇所ある。いずれにしても水を補給していかないと小屋には備えは無いので何処かには寄って行かなくてはいけない。黄連と白鳥は枯れることもあるとのことで北又は問題ないらしいが、今朝出発した朝日小屋の情報では黄連も大丈夫とのことだった。自分の場合は夕、朝食、行動用に2リットルは必要で、できれば泊まる予定の場所から近いところのほうが重くならなくて歩くには楽ができる。
この時点では拇指球の痛みはさほどでもなく、この分なら栂海山荘には泊まらなくてもよさそうだ。ということで北又はパスすることにした。
崩れかかったヤセ尾根を通り犬ヶ岳に到着。

目の前に小屋が見え、更に遠く、一番奥の山の上になにやら光っている構造物が小さく見える。

あれが白鳥小屋なのか…?ものすごく遠くに感じ、なんだか気持ちが折れそうになる。
栂海山荘12時到着。朝日小屋から既に7時間半たったことになる。

休憩を兼ねて栂海山荘を見学。声をかけたが誰もいなかった。
入り口は二つあり、入ると土間、テーブルがある。テーブルのところにはこの建物の歴史写真があって歳月と共に小屋が大きくなっていく様がわかる。献金箱があり一泊2000円とのこと。土間のところには荷物置き場があってその奥に山小屋のような蚕棚のベットがあり、毛布が備えられている。


表のベンチに腰掛けながら、迷った。ここから先、白鳥小屋までのコースタイムは3時間半。休憩も入れると4時間はかかるだろう。時間が遅くなれば疲労も溜まり、さらに時間はかかるかも知れない。足の拇指球も心配だ。予備日はみているが白鳥まで行ければ翌日は楽になるだろう。仮にたどり着けなくとも途中でテントを張れば良い…などなど考えて結局、白鳥を目指すことにした。
栂海小屋からの下りは急でしかも長い。この辺りから樹林帯に変わっていく。そして登山道は土っぽくなり、所々ぬかるんでいたためスリップし易い。もし雨が降っていたら大変だったろう。
黄連山を越えて黄連ノ水場分岐到着。

白鳥の水場は枯れているかも知れないのでここで補給することにした。往復10分とのことだったが時間はもっと短かった。水の流れはほとんどなかったが、ダムのように堰き止められていた水溜りから汲んだ。
ザックに入れ背負ってみると明らかに重くなっていた。わずか2kgでも疲労した体には堪える。そんな気持ちを癒してくれたのは辺り一面のブナの林だった。
新潟の十日町に「美人林(びじんばやし)」というブナ林の名所がある。人間の手は入っているのだろうがそれは美しい林で、木が、森が、美しいと感じたのは初めてだった。黄連山周辺のブナは高さは無かったがやっぱり美しかった。
黄連、菊石、下駒ケ岳、白鳥とピークを越えるように道が作られているが「朝日から歩き始めて最後にこのピーク越えは本当に辛いよ」とは聞いてはいた。歩くと下りは拇指球が痛く大変だが登りは問題なし。ずっと登りが続けば良いと心の底から思っていた。
菊石山を下り、下駒ケ岳の基部で休憩。靴を脱いで足を休ませる。体力的には問題無いのに登る前からわかっていたのに、後悔先に立たずとはこのこと。帰ったらインソール真剣に考えよう・・・
トラロープがある急登を登り、ガレ場を歩き下駒ケ岳14時25分到着。

白鳥小屋まであとどのくらいなんだろう?ふと顔を上げたび、木々の間から白鳥小屋が見えるがまだ遠いように感じる。
白鳥の水場。水は黄連で汲んできたから必要ないのでスルーしたが、改めて水の重みが体に圧し掛かる感じがする。
空が近くなってきている。確実に高度を稼いでるのは分かるが、上がったり下りたりしているので次のピークの先にゴールがあるのか分からない。
このピークの先にもまだ道が・・・と思ったら、白鳥小屋到着。なんだか拍子抜けした本日のゴールだった。

15時30分、朝日小屋から11時間だった。
小屋に荷を降し登山靴、靴下を脱ぎ捨て、サンダルに履き換える。開放感がたまらない・・・
固まった体を解し、建物の上にある展望台に上った。

目の前に日本海が広がる。天気も良く能登半島も確認することが出来た。
小屋には自分ひとり。この時間だ、貸しきりで泊まらせてもらうことになるのだろうと、思っていたら・・・つづく
Posted by うまそう at 10:44│Comments(0)
│9月・北アルプス